前立腺が加齢で肥大し、トイレが近い、尿が出にくいなどの排尿障害を起こす病気です

前立腺肥大症は、中高年男性に多くみられる疾患で、前立腺移行帯の過形成により尿道が圧迫され、排尿障害を引き起こします。症状は排尿困難(尿線細小、遷延、残尿感)や蓄尿症状(頻尿、夜間頻尿、尿意切迫感)などがみられ、進行すると尿閉や膀胱機能低下、腎後性腎不全を来すこともあります。
診断には超音波による前立腺体積測定、尿流測定、残尿測定などを行います。治療はα1遮断薬や5α還元酵素阻害薬を中心とした薬物療法が第一選択で、効果不十分例には手術療法が考慮されます。早めの受診によって、快適な生活を取り戻すことが可能です。
膀胱が過敏になり、頻尿や急な尿意、尿漏れなどを引き起こす状態です

過活動膀胱は、膀胱が過敏になり、自分の意思とは関係なく頻繁に尿意を感じる状態を指します。加齢とともに増加し、男性・女性ともにみられる病気です。脳や脊髄からの神経信号の乱れや、膀胱自体の筋肉(排尿筋)の異常な収縮が原因とされています。軽い症状でも、日常生活や睡眠の質に影響を及ぼすことがあり、我慢せずに相談することが大切です。
治療は生活習慣の見直しや骨盤底筋体操、薬物療法が中心で、難治性の場合には薬物の膀胱壁内注射も行います。恥ずかしさから受診をためらう方もいますが、適切な治療によって改善が期待できます。気になる症状があれば、早めのご相談をおすすめします。
脳や脊髄、末梢神経の障害で膀胱の働きが乱れ、排尿異常を起こす状態です

神経因性膀胱とは、膀胱や尿道の排尿機能が、脳・脊髄・末梢神経など排尿に関わる神経の障害によって正常に働かなくなる状態を指します。中枢性(脳血管障害、脊髄損傷、パーキンソン病など)と末梢性(糖尿病性神経障害、骨盤手術後の神経損傷など)に大別されます。
排尿筋が過剰に収縮して頻尿・尿意切迫感・失禁を引き起こすタイプ(過活動型)と、収縮できず排尿困難や残尿、尿閉、溢流性尿失禁をきたすタイプ(低活動型)があります。診断には排尿日誌や残尿測定、尿流測定、膀胱内圧測定などが用いられ、治療は薬物療法、自己導尿、電気刺激療法など、病態に応じて行います。
細菌が侵入し、腎臓や膀胱、前立腺、精巣上体などで増殖して感染を起こす病気です

尿路感染症は、尿路(腎盂、尿管、膀胱、尿道)に細菌が侵入・増殖して起こる感染症で、女性に多くみられます。最も一般的なのは膀胱炎で、排尿時痛、頻尿、残尿感、尿混濁などの症状が現れます。腎盂腎炎まで進行すると、発熱や背部痛、倦怠感など全身症状を伴います。原因菌の多くは大腸菌など腸内細菌で、性交渉、排尿後の清拭方法、尿の停滞などがリスク因子です。男性では前立腺炎を伴うこともあり、高齢者では無症候性の場合もあります。診断には尿検査や尿培養が行われ、治療は適切な抗菌薬の投与が中心です。再発を防ぐため、基礎疾患の評価や生活習慣の見直しも重要です。
性行為を介して感染し、泌尿生殖器や全身に症状を及ぼす病気です

性行為感染症は、主に性的接触によって感染する疾患の総称で、細菌、ウイルス、原虫などさまざまな病原体によって引き起こされます。代表的な疾患には、クラミジア感染症、淋菌感染症、梅毒、トリコモナス症、マイコプラズマ感染症、HIV感染症、尖圭コンジローマ、ヘルペスなどがあります。男性では尿道からの分泌物、排尿時の痛み、陰部のかゆみや発疹などの症状が現れることが多いですが、無症状のことも少なくありません。未治療のまま放置すると、不妊症や慢性炎症、他人への感染拡大の原因となることもあります。診断には、尿検査、分泌物の培養・PCR検査、血液検査などが用いられます。
前立腺がん、腎がん、膀胱がん、腎盂尿管がん、精巣腫瘍など多岐に渡ります
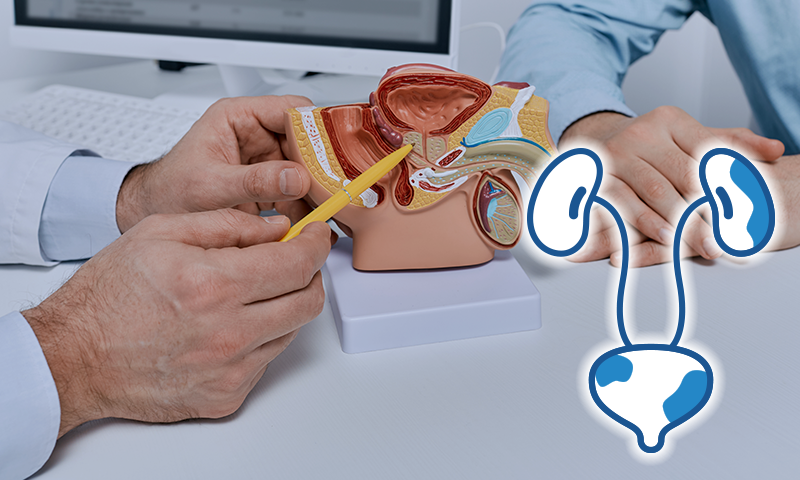
中高年男性に多く、男性の癌では最も多い癌です。早期は無症状のことが多く、血液検査(PSA)で発見されます。治療は手術、放射線、ホルモン療法などがあります。
腎臓にできるがんで、進行すると血尿や側腹部痛が現れますが、初期は無症状であり、画像検査で偶然見つかることが増えています。主に手術で対応し、転移例では分子標的薬や免疫療法を行います。
血尿で見つかることが多く、喫煙がリスク因子です。内視鏡による切除や膀胱内注入療法が初期治療の中心で、進行例では手術や抗がん剤治療が行われます。
腎臓から膀胱へ尿を運ぶ通り道にできるがんで、膀胱がんと同様に尿路上皮がんに分類されます。血尿が主な症状で、診断・治療には内視鏡や手術が用いられます。
若年男性に多く発症し、精巣の腫れやしこりで気づかれます。治療は手術に加え、化学療法や放射線治療を行い、治癒率は比較的高いのが特徴です。
尿の成分が結晶化して結石となり、腎臓や尿管・膀胱などに詰まって症状を起こします

尿路結石症は、腎臓・尿管・膀胱・尿道など尿の通り道に石(結石)ができる病気です。結石が尿の流れを妨げると、激しい腰やわき腹の痛み、血尿、吐き気などを引き起こします。原因は、水分不足や食生活、体質、代謝異常などが関係しています。小さな結石は自然に排石されることもありますが、大きな結石や痛みが強い場合は、薬物治療、体外衝撃波破砕術(ESWL)、内視鏡手術などが必要になります。再発しやすい疾患のため、食事指導や水分摂取の工夫が重要です。
勃起障害(ED)・男性型脱毛症(AGA)の自費診療が可能です

勃起障害(ED)は、満足な性行為を行うために十分な勃起が得られない、あるいは維持できない状態を指します。加齢に伴う血管や神経の機能低下、糖尿病・高血圧・喫煙などの生活習慣病、ストレスやうつなど心理的要因も関与します。治療には、内服薬(PDE5阻害薬)が主に用いられ、高い効果が期待できます(自費診療)。
AGAは、思春期以降に額の生え際や頭頂部の毛が徐々に薄くなる、進行性の男性型脱毛症です。男性ホルモン(DHT)の影響で毛包が縮小し、髪が細く短くなることが原因です。治療は、内服薬(フィナステリドやデュタステリド)や外用薬(ミノキシジル)などがあり、継続することで進行を抑制できます(自費診療)。
加齢に伴い男性ホルモンが減少し、疲労感や倦怠感などの症状が現れる状態です

男性更年期(加齢男性性腺機能低下症、LOH症候群)は、中高年以降の男性にみられる、男性ホルモン(主にテストステロン)の分泌低下に伴う心身の不調を指します。主な症状には、疲労感、意欲の低下、抑うつ、性欲減退、勃起力の低下、睡眠障害、集中力の低下などがあります。症状は個人差が大きく、ストレスや生活習慣も影響します。血液検査でテストステロン値を測定し、症状と併せて総合的に診断します。治療はホルモン補充療法や生活改善を行います。
精液検査、ホルモン検査、画像検査などを行い、薬物療法や手術等の治療を行います

男性不妊症は、妊娠を希望するカップルのうち、男性側に原因がある場合を指し、全体の約半数に関与するとされています。主な原因には、精子の数が少ない、運動率が低い、奇形率が高いなどの造精機能障害、精索静脈瘤、ホルモン異常、射精障害などがあります。検査は精液検査、ホルモン検査や画像検査を行い、原因に応じて薬物療法や手術、補助生殖技術(人工授精・体外受精)などが選択されます。
泌尿器科では尿潜血陽性、尿蛋白陽性、腫瘍マーカー異常などが指摘されやすいです
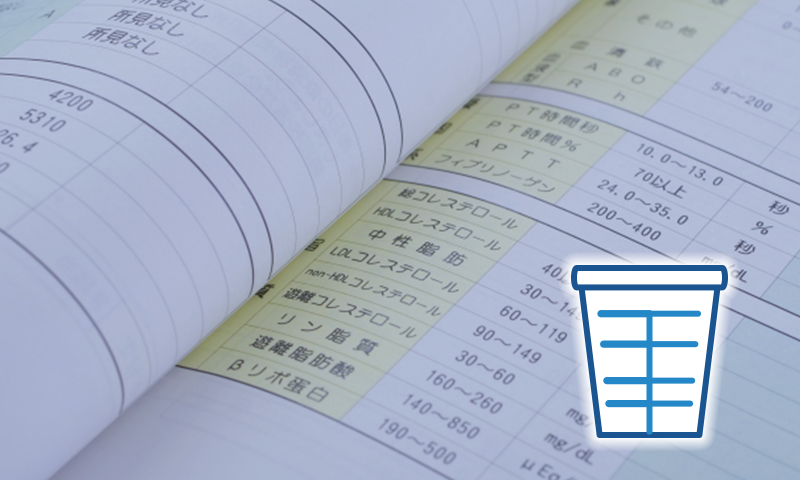
健康診断において泌尿器科領域では尿潜血陽性、尿蛋白陽性、腫瘍マーカー異常などが指摘されやすいです。
尿中に血液成分(赤血球)が混じっている状態で、顕微鏡レベルの微量な血尿でも陽性になります。原因は膀胱炎、尿路結石、前立腺肥大、腎炎、腎腫瘍など多岐にわたり、無症状でも重大な疾患が隠れていることがあります。
腎臓の濾過機能に異常があると、通常は尿に漏れない蛋白が排泄されるようになります。一過性の軽度なものもありますが、慢性腎炎や糖尿病性腎症、腎硬化症などの初期徴候であることもあります。繰り返し陽性の場合は腎機能検査や専門医の診察が必要です。
腫瘍マーカーはがんの存在や活動性を示す血液検査ですが、がん以外の良性疾患や加齢、炎症でも上昇することがあります。たとえばPSA(前立腺特異抗原)は前立腺がんだけでなく前立腺肥大や炎症でも上昇します。異常値が出た場合は、追加検査や画像診断による精査が必要です。